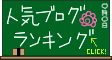› ひねりてのお直ししまSHOW › 2017年05月
› ひねりてのお直ししまSHOW › 2017年05月・インスタグラム始めました

ブログ以上に店主の趣味嗜好をご紹介してますので
良かったらご覧ください。
「いいね!」と「フォロー」で応援していただけると
嬉しいです

ひねりてインスタグラム
・このブログは
広島近郊の方には、お店の詳細を知っていただくために
遠方の方には
身近なものを修理して使用する楽しさをお伝えするために
公開しております。

・右下の方にあるカテゴリの、一番上の記事
「ひねりてからのおことわり」の内容にご了承の上
ご来店ください。

・ブログ内で、過去に修理した作業内容や価格
納期などをご紹介しておりますが
同じ修理内容でも対象商品の状態や仕上げ方などによって
価格や納期は変わります。
あくまで目安として
参考にしていただくために公開しておりますので
予めご了承ください。

・2014年4月より前の記事では
その当時の消費税率5%で価格表示してありますが
実際にはご来店時点での消費税率で
対応させていただくこととなります。

・当店は予約制ではありませんので
営業時間内のご都合の良い時に、修理したい商品と
どんな修理にしたいかという構想を持って
ご来店ください。

場合によってはお客様が集ってしまうこともありますが

その際は、携帯電話をお持ちの方には
店外で他の用事などをしてお待ちいただき
受付の順番になったら、ご連絡させて頂いております。

2017年05月27日
梅雨前のご提案
こんにちは
昨日はひねりて出演のラジオの放送日でしたが
恐る恐る聞いてみた感想を言いますと
ひねりての話方が
語尾延ばし過ぎ~、ごまかし笑いし過ぎ~
って感じでした



でも、内容については
やはりプロのDJの方の誘導と
編集の腕のお陰で
なんだかいい感じにまとまってたなと思いました。
周りの方々の反応も良い感じで、ちょっとホッとしております。
貴重な経験をさせていただきました

さて、今日はこれからの季節によくある
革製品のトラブルを予防するためのご提案を
少しさせていただきたいと思います

その1
年に1~2度使うか使わないかの長期保管中の商品を
保管場所から出して点検してみましょう

これから梅雨に入るとともに

革製品などの保管場所の環境は
高温多湿になりがちかと思いますが

そうすると起こってくるのがこういう現象です

内張りなどに使われている合皮素材が
ベタベタポロポロ・・・

さらにその劣化物が、
中に入れたあらゆるものについてしまって
取れなくなるという2次災害にもつながる厄介な現象です

で、この予防に有効なのが定期点検です

毎年衣替えのついでに鞄や靴、帽子などなど
年に数回しか使わないような商品を
「相変わらずかわいいなぁ かっこいいなぁ
かっこいいなぁ などと」
などと」
 かっこいいなぁ
かっこいいなぁ などと」
などと」愛でてあげながら、全体を点検してみてください

こうやって新鮮な空気に触れさせてあげることで
合皮の劣化を進みにくく出来るだけでなく
パッと見では気づけない汚れやきず、
ほころびなどなどを早期発見&早期対処ができて
一石二鳥ですよ

さらに可能であれば
乾燥した天候が続く時を見計らって1週間程度

通気の良い室内の日陰に出して
しばらく湿気などを飛ばしたうえで
保管場所に戻してあげるとなお良いです

その2 見つけた汚れは綺麗に取り除いておきましょう

この時期にすくすく育つのがカビ君

カビが健やかに育つ条件は
・高温
・多湿
・高栄養
この三つが揃ったときです

で、汚れはカビの栄養ですから
目につく汚れだけでも、出来るだけ取り除いておいてあげましょう

もう一つ
これはひねりて的な見解ですが
お手入れ用品のクリームやオイルも
カビにとっての栄養にもなり得ると思っています

そういう意味では
長期保管前の過剰な栄養補給は危険かと・・・

ということで
比較的リスクの少ない方法として
長期保管前は汚れを取り除くことを重視し
栄養補給は程々、もしくはしないでおいて
使用し始めるお手入れの時に
程良く栄養を与えてあげる

という方法が良いと思います

その3
革製品の近くに塩化カルシウム系の除湿剤は
使用しないようにしましょう

塩化カルシウム系の除湿剤とは
よく押し入れやクローゼット用に販売されている
湿気を吸い取るとジェル状になるものや
水溶液が容器の底にたまるタイプの除湿剤の事です

ここ最近は
ご存知の方も増えつつあるかもしれませんが
いまだにある悲しいトラブルとして
この塩化カルシウム系の水溶液が革について
革が収縮硬化するなどの変化をして
商品として使えなくなってしまうというものがあります

こうなってしまったら元通りは無理で

上から何かワッペンなどを縫い留めるか
その部分のパーツをすべて交換するなどの
大掛かりな作業が必要になります

ということで
革製品の近くに乾燥材を置くなら
シリカゲル系にしておくことをお奨め致します

その4
長期保管する場合は
保管場所の中でも床から離れた場所を選びましょう

床に近いほうに湿気は溜まりがちなので

床から離れた棚の上や
クローゼットや押入れの上の方に保管しておいた方が
より安全だと思います。
その5
雨の日は革製品の使用は避けるか
防水スプレーやワックスで保護してあげましょう

革製品、特に天然仕上げの革は雨にぬれれば
なにかしらの影響は受けるものです

「シミも傷も皺も味のうちで、かっこいい!」
という方は何も気にせず
ガシガシ使われても構わないと思います

ただ、何もメンテナンスすることなく濡れて乾いてを繰り返せば、
劣化するのも早いですので

そこは覚悟の上で取り組んでくださいませ

「いやいややっぱりシミも傷も最低限にして
末永~く愛用したいです~ 」
」
 」
」って方は、雨の日は使用しないのが一番リスクが少ないです。
雨でも使いたいという方は
出かける20分ほど前に防水スプレーをかけて
スプレー用液がしっかり乾いた状態で使用し
濡れた場合は、出来るだけ早く水分を拭きあげてください

スプレーではなく
出来るだけ自然な方法で予防したいという方には
ロウ成分がしっかり入ったワックスで革表面をコートして
すぐに水分が浸み込まないようにすることで
シミになりにくく保護することは出来ます

ただ、これこそついた水滴は
すぐにふき取るようにする必要がありますので
その点は注意してくださいね

ちなみにロウ成分がたっぷり入ったワックスは
タピールの商品で言うと
レーダーフレーゲクリームになります

しかし、これだけ用心していても
不意の雨にあってしまうこともあるでしょう

もし革製品が濡れてしまったら
部分的に濡れた場合
濡らした綺麗な布で拭いて、思い切って全体を濡らしてください

もちろん濡らす量は必要最低限にして、
余分な水分はしっかり拭き取って下さいね

そのうえで出来るだけ速やかに乾くように
詰め物をこまめに取り換えたり、向きを変えてあげてください。
ドライヤーやストーブなどの高熱をあてるのは厳禁です、
革が変化して元に戻らなくなりますから注意してくださいね

全体に濡れてしまった場合は
部分的に濡れた時同様、
余分な水分はしっかり拭き取ったうえで
速やかに自然乾燥できるように
せっせと世話を焼いてあげてくださいませ

しっかり乾いたら
必要な水分や油分まで飛んでしまってますので
それを補うメンテナンスをしてあげてください

タピールで言うと
レーダーオイルやレーダーフレーゲ、
レーダーバルサム、レーダーフェットあたりが良いと思います

と、ざっくりこんな感じでしょうか?
商品の状態、その時の状況によって
より良い対処方法も違うので
なかなかはっきり言うのは難しいですが
以下の事だけしっかり覚えておいてください

・高温多湿、高栄養な状態にしないこと
・塩化カルシウム系の除湿剤の溶液を革につけないこと
・部分的に濡れてしまったら全体を同じように濡らすこと
・濡れた時に高熱を与えないこと
とりあえずこれを気を付けておけば
大きなトラブル と悲しい思い
と悲しい思い を
を
 と悲しい思い
と悲しい思い を
をずいぶん減らせると思います

では、皆様が今年の梅雨もトラブルなく
潤いだけを手に入れられることを願っております

2017年05月20日
ひねりて、初のラジオ出演のお知らせ
どうもどうも、
ひねりて、この度初めて
ラジオに出演させていただくことになりましたので
以下の通りお知らせさせていただきます

日時
5月26日(金) AM10:15~10:30
番組名
ヒロシマ ウィメンズ ハーモニー
番組ブログ
「初めての割にはリラックスしてお話出来たなぁ」

という印象ではありましたが
行く前までは、収録に行ったら写真を色々撮って
ここで皆様にご報告をしようと思っていたのに

いざ行ってみると、
収録終えてスタジオを出た後になって
一枚も写真を撮っていなかったことに気づく始末・・・

やっぱり舞い上がってたんですねぇ



なので写真は一枚もございません~、すみません

そして、ひねりてがリラックスしてお話しできたのは
やはり進行役のDJ、
宮前さんのなせる業だったのだと思います

とても話しやすい、気軽な雰囲気を作ってくださいましたので
いくらでも話せそうな気分になれましたよ



収録自体は放送時間より長く撮ってありますが
どんな風に編集してくださっているのかが楽しみです

ただ、放送当日は
スタジオで撮っていただいた番組ブログ用の写真と
ラジオから流れる聞きなれない自分の声に
きっと違和感と恥ずかしさを感じるんだろうなぁ



とも思って、
今はなんだか変な気分です



何はともあれこの年になっても
こういう新鮮な気分を味わえる機会を頂けるのは
ありがたいことですよね

放送日が平日の午前ということで
当日聴ける方は限られるでしょうが
もしちょうどタイミングが合うようでしたら
良かったら少しだけ耳を傾けてみてください

ひねりてがDJの方に
うま~く転がしてもらってますから



2017年05月12日
The REAL McCOY'S フライトジャケットの袖口リブとファスナー交換(after)
こんにちは、
え~、つい先日のことですが、
たまたまブログの過去記事を見直していた時に
気づいてしまいました・・・

ひねりて、ひとつ修理仕上がりのご紹介をし忘れていましたね

この2か月
「あの革ジャンの仕上がりはどうなったんだろう?」と

もやもやしていた方もいらっしゃったのではないでしょうか・・・
すみません

ではさっそく・・・
商品はこちらのフライトジャケット

修理前の記事は2か月も前の事ですので
忘れてしまったという方は
まずはこちらで再度内容をご確認くださいませ

で、今回見直していてさらに気づいたことは
前回載せていた写真はすべて仕上がり後の写真でした

どおりでどこも傷んでいるところが見当たらないわけですよねー
結局修理前の写真は取り忘れていたようです

・・・重ね重ね混乱させてしまって申し訳ありませんでしたー

でも無いものは仕方ない・・・

ということで
今日は仕上がりをさらに詳しくご覧くださいませ

材料はミリタリー専門ショップで
タロンのファスナーと
まさにオリジナルそのものともいえる復刻リブニットを仕入れて
取り付けました

修理前のリブはこんな感じです
こうなったらもう取り替えるしかないですね

オリジナルと比べてみていかがでしょう?
毎度のことですが
手回しのミシンで一目ずつ元の針孔に針を落として縫っていますので
傷みを最小限に抑えることが出来ています

内側はこんな感じ
違和感なく仕上がってます

修理前のファスナーです
こちらもジャケットのファスナーによくある症状で
こうなってしまったらやはり交換するしかありません

今回修理させていただくことで

フライトジャケット
タロンファスナー交換55㎝
リブ交換(両袖) 23000+税+8100(特注材料費)円
修理期間 1か月
(仕入れ等期間含まず)
オーナー様のご希望で
時間をかけて出来る限りオリジナルに近い材料を探し
修理させていただきましたので
費用も期間も通常以上にかかってますが



それだけに
ほぼオリジナルと変わらない仕上がりに出来たと思います

材料仕入のためなどにいろいろ情報収集してみて
どうやらこちらの商品が
マニアの方々にはたまらない一品であるらしい
ということにじわじわ気づいてきました


確かに色合いといい質感といい
雰囲気のあるいいジャケットだなと思いますし
仕立てもしっかりしてあるなという印象深い一品でした

こうやって上質な一品に出会えるのも
このお仕事の楽しみのひとつです

最後に、見た目には丈夫に見えたジャケットですが
やはり年数がたってる分乾燥していましたので
レーダーオイルでしっかり栄養を与えて
もっちり肌に整えさせてもらいました

オーナー様にも喜んでいただけたので良かったです

ご利用を検討中の皆さまはどうぞこちらでご確認くださいませ


2017年05月07日
オーストリッチハンドバックの内張り交換
こんにちは
本日ひねりては営業中です

日曜の営業日はなかなかないですので
この機会に皆さま
GW中に見つけてしまった眠れる宝物!?

をお持込くださいませ

本日の商品はこちら
まるで双子のように見えるのも当然
同じ鞄の色違いです

色合いの感じからなんだかクリスマスを連想してしまいますね

今回のご依頼はどちらも内張り交換です。
こんなお部屋がありましたぁ

今回は二つとも
この部屋は修理せずにそのままにしておいて
開かずの間にするということでした

では仕上りご覧ください

内張りの色は鮮やかな朱色

こちらの内張りの色は少し押さえめのワイン色

赤がお好きな方のようです

なんだか元気の出てくる色合いですね

このポケットは元の革を使用して同じように作り替えてあります

内張り交換(上部部屋側のみ)
ファスナー付内ポケット1個
内ポケット1個 X2 48000+税円
作業期間 約1か月
これで今年のクリスマスは活躍してくれそうです

って、気が早すぎたかな・・・

今日でGWも幕を閉じますね

それにしても今年はほぼお天気に恵まれて

初のGW休みを頂いたひねりても
川沿いのベンチで探鳥しつつのブランチをとるなど

のんびり穏やかな休日を過ごさせていただきました

「ああ、贅沢だなぁ・・・」と思わずひとりごちてしまうほど
なんとも心地よいひと時でした

皆さまはどんな時間を過ごされましたか?
きっと明日からの力の元を
たっぷり蓄えられたのではないでしょうか



ひねりては次の贅沢な時間を楽しむために
またご褒美の積み立てをしていきたいと思います