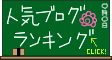› ひねりてのお直ししまSHOW › 2014年05月
› ひねりてのお直ししまSHOW › 2014年05月・インスタグラム始めました

ブログ以上に店主の趣味嗜好をご紹介してますので
良かったらご覧ください。
「いいね!」と「フォロー」で応援していただけると
嬉しいです

ひねりてインスタグラム
・このブログは
広島近郊の方には、お店の詳細を知っていただくために
遠方の方には
身近なものを修理して使用する楽しさをお伝えするために
公開しております。

・右下の方にあるカテゴリの、一番上の記事
「ひねりてからのおことわり」の内容にご了承の上
ご来店ください。

・ブログ内で、過去に修理した作業内容や価格
納期などをご紹介しておりますが
同じ修理内容でも対象商品の状態や仕上げ方などによって
価格や納期は変わります。
あくまで目安として
参考にしていただくために公開しておりますので
予めご了承ください。

・2014年4月より前の記事では
その当時の消費税率5%で価格表示してありますが
実際にはご来店時点での消費税率で
対応させていただくこととなります。

・当店は予約制ではありませんので
営業時間内のご都合の良い時に、修理したい商品と
どんな修理にしたいかという構想を持って
ご来店ください。

場合によってはお客様が集ってしまうこともありますが

その際は、携帯電話をお持ちの方には
店外で他の用事などをしてお待ちいただき
受付の順番になったら、ご連絡させて頂いております。

2014年05月31日
ルイヴィトン ボストンバックのリメイク その2
おかしいですねぇ、
たしか明日から6月だと思うのですが
まるで7月に入るのではないかと思える暑さ

そろそろ苦手な季節が近づいてきているようです

さてお待たせしました、前回の結果発表です

まずオリジナルのワッペンについてですが
作成する柄はこちらです



丸に剣方喰 丸に揚羽蝶
*上記画像資料はグーグルの画像一覧から引用しております。
揚羽蝶のほうは線が多くて複雑なので
うまく仕上げられるか不安でしたが

こんな感じに仕上がりました

丸に剣方喰
丸に揚羽蝶
モノグラムになじむ濃茶色のオイルレザーに
モノグラム柄の色に近い黄土色系の糸を使って
八方ミシンで形を縁取ってあります

アゲハチョウのほうの
羽の模様と目の部分には
ゴールドのカシメを使いました

どうでしょうか?
このワッペンに関しては作業内容をいろいろ思案したうえで
2パターンの方法をご提案させていただき
オーナー様と念入りに打ち合わせをした中でこの方法に決まりました

革、カシメ、糸色も全て目で見て選んでいただいてます

ひねりての率直な感想はというと
大変だったぁ

何とか形に出来て良かったぁ

新しい挑戦が出来て楽しかった~

が交錯している感じです。
仕上がりだけ見たら
すっきりまとまって見えるかもしれませんが
ちょっとだけ途中の状況をお伝えしますと

表 裏
縫いあがった時はこんな状態でした

最初の予定ではもっと一筆縫いのように
1回の針入れで何度も縫い重ねて仕上げるつもりだったのですが・・・
何度も縫い重ねると針で糸を切りやすいという事情や

細い線と太い線を混在させて
メリハリのある柄に仕上げたいという思いから

何度も針を入れ直して縫う方法にしました。
その結果がこのわさわさ状態です

そしてコツコツちまちま糸処理をしまして・・・
こういう状態に仕上げました

表 裏
これを本体に縫い留めますと
この時点でけっこういい感じに仕上がりそうな予感

いやいやまだまだ先は長いぞ

油断は禁物

これからマチを取り付けて組み立てていくわけですが
これまた予想外のことが勃発しちゃったんです



では毎度のことですが
この続きは次回にしますね

お楽しみに

2014年05月24日
ルイヴィトン ボストンバックのリメイク その1
今日は以前告知しておりました、
新しく挑戦した修理についてご紹介させていただきます

商品はこちらのボストンバック

サイズと装備からして
おそらくキーポル・バンドリエール55というタイプと思われます

何かとご利用いただくお得意様の鞄で
以前から「こういう鞄があるんだけど・・・」
と相談を持ち掛けられていたものでした

で、どこを直したいのかというと・・・
パイピング近くと、
そこから3センチほど離れたところの樹脂部分が擦れて
穴が開きかけてます

さらに角度を変えてみると、
パイピング付近は底の方まで擦れてます!

反対側のパイピング付近も・・・
やっぱり擦れてますね

オーナー様のご希望は
この擦れた部分が無くなるくらいまで両サイドをカットして
サイズを小さくすることがひとつ

それからもうひとつは、
お気づきかと思いますが、以前どこかの修理屋さんで
擦れがひどかった部分に革をあてて修理してもらってます。
その部分にもう少し周りと馴染むような
オリジナルのワッペンを作成して取り付ける

ということでした。
で、オーナー様とともにあれこれ思案した末に
オーナー様のご両親の家紋を表現したワッペンを作成して
取り付けるということになりました

このアイデアはオーナー様からのご提案です。
ルイヴィトンのモノグラムは
日本の家紋に触発されていると聞いたことがありますし

そのエピソードがなかったとしても、
この柄に家紋はぴったりだと思います

それがまたご自分にゆかりの家紋となれば
愛着も人一倍湧くこと間違いなしですよね

さすがオーナー様、素敵なアイデアです

こんな風にご希望とアイデアがいい感じにピタッとはまった時

ひねりても嬉しくなって作業するのが楽しみになります

それでは、気分も盛り上がってきたところで、分解っ!

つづきは
次回のお楽しみです

ちょうど先ほどオーナー様が引き取りにご来店されました

当の鞄はお店の棚の特等席に鎮座してたのですが

お店に入ってくるなりオーナー様は一言
「かっこいい!」

この反応で一気にひねりてのテンションが上がったことは
言うまでもありません

では次回の仕上がり報告をしばしお待ちくださいませ

Posted by ひねりて at
17:38
│Comments(0)
│修理(ほころび、革あてなど)│修理(アレンジ)│LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)│鞄│修理(革部品交換、大物修理など
2014年05月17日
BREE書類鞄、擦り切れ補強修理と持ち手等交換 その3
いいお天気ですねぇ

カープも好調をキープしてくれてるし

お蔭でひねりても気持よくお仕事できております



さあでは、今日も前回の続きですね

今度はこの部分

前
横
後

最初にもお伝えしましたが、この鞄は
分解しても、組み立てるのが大変困難な構造になっているため
今回は分解しないで出来る方法で作業させていただきました

底の擦り切れ部分を全体的にカバーできて
なおかつ見た目にも馴染み

マチのファスナーの使い勝手にも問題が生じないように

オーナー様と相談しながらこのようなデザインに決めましたが
いかがでしょう?

この方法だと
底の部分は本体に縫いつけることが不可能なので
先に飾りステッチを入れておいて
本体へ出来るだけ接着しておいたあと
このように3か所にカシメを打つことでしっかりと留めてあります

底以外の前、横、後の部分は
3回に分けてミシンで本体に縫いつけてます

と言ってしまえば簡単ですが

この鞄自体、厚い革を使用しているうえに
内張りとの間にはスポンジのクッションが入っており

そこにさらにこのカバーを足して縫うというのは
かなり厚みが出て縫いにくいものでした

というわけで今回の修理のなかで
この底カバー取り付けの作業が一番の難関でした



その他の修理は以下の通りです

背面底近くにあるファスナーの引手がとれたところに
革引手を作成とりつけています。
もともとは金属製の引手がついてましたが、
同じようなものを取り付けるにはスライダーごと交換する必要があり
構造上高額になってしまうので、
一番簡易的にできる方法で修理してます

場所的に目立たないところである上に
引手をファスナーのカバーに入れ込めば(上写真右)
ほとんど見えないので気にならない感じです

一方でこちらも同じように革引手を取り付ける予定でしたが
スライダーの構造が上記のものとは違って
同じ革引手を良い具合に取り付けることが出来ない
ということを作業中に気づき

急きょスライダー交換へと変更して以下のような仕上がりになりました。
左マチ(修理した側) 右マチ
修理したのは左マチのほうです。
この部分に関しては
スライダー交換がスムーズに作業出来る構造だったので
料金を追加することなく作業変更させていただけました

こちらも結果的には
遠目に似た仕上がりに出来たので良かったです

あと、こちらは鞄の中の仕切りについている
面ファスナー(マジックテープ)のループ側ですが
劣化して外れかけていたので新しく交換しています

元より大きいサイズのものを裏に貫通させて縫い付けました。
こちらは面ファスナーのフック側が先についたベルトの付け根で
内張りへの取り付け部分がほころんでとれかけているのを
縫い留めました。
この作業
持ち手の取り付け時に分解したついでに
ちゃちゃっと縫い留められると予想して受け付けたのですが・・・
これまた予想外の構造になっておりまして、
予定通りの作業は出来ませんでした

文章でのその説明は
ひねりてにはちょっとうまく出来そうにないので省きますが
かなり冷や汗かきながらの作業内容となりました



最終的には予定より丈夫に縫止められたので一安心です

裏は外ポケットの内張り部分に貫通させてます

同業者の方ならこれがどういう状況であったか
察していただけるのではないかと思います

そんなこんなの手に汗握る展開だらけの作業を経て
完成に至ったわけであります

最後にコーナー部分など全体に色が剥げているところが
目立たなくなるように黒い顔料を添付し
革への栄養とつやも与えて仕上げてあります

BREE書類鞄
持ち手、根ももX2交換
底角革カバー(両サイド)
スライダー(引手付)交換
革引手作成取り付け
面ファスナー交換X1
ベルト付け根ほころび縫い
全体色はげ部分、着色処理 67000+税 円
納期(革仕入あり) 約2か月
今回はほんとに初めてのことと予想外のことだらけで
とても貴重な経験をさせていただきました

この鞄を分解してみて感じたのは
かなり厳重に頑丈に作成されているなということで
さすがBREEさん
しっかりいい仕事をされてました

ただ、今回の修理に関しては・・・
それが大きな障害になってくれちゃいましたけどね~



これからこの鞄が1日でも長く
オーナー様のもとで活躍してくれることを切に願います

2014年05月10日
BREE書類鞄、擦り切れ補強修理と持ち手等交換 その2
お待たせしました
前回の続き、BREE書類鞄の結果発表です

ざっと見た感じはいかがでしょうか?
ではまず持ち手部分から近づいてみましょうね

修理前はこんな感じでしたが・・・
持ち手はこのように再現しました

なんでも多めに盛りたい性分を今回も制御できず

元より中の芯も表の革も少し厚めにし
せっかくだからお気に入りの丈夫なナイロン芯も
この際たっぷりしっかり入れ込んで・・・
などといろいろ盛りに盛ってしまったため

結果厚みが元の1.5倍の12㎜

当然予定していたミシンでは縫えないため



手縫いで仕上げるという墓穴を掘ってしまいました

もちろん鞄とオーナー様にとっては良いことで、
元よりかなり強度は上げられています

と自信を持って言えるものに仕上げられたので
最終的には良かったと思います

根ももはこんな感じ
修理前
修理後
オーナーさまにはご了承済みですが
リベットはBREEのロゴなしに変わってます

こうやって元と比べると
ちょっと用心してステッチを内に入れすぎちゃったかなぁ?

とは思いましたが
中の芯はもとより強度を維持してくれるものにしてあるし

やはり常に重い荷物を運ぶ役割であるこの鞄の
一番重視すべきは耐久性なので

そういう点では良い修理に仕上げられていると自負してます

ここで芯材についてひねりての考え方と作業方法を
少しご説明させてください

もともと入っていたスチール芯です

最初はかなり頑丈だと思うのですが

使用回数の増加に比例して金属疲労を起こし
このようにポキッと折れてしまいがちのようです

実際こういう症状で持ち込まれた鞄を

数多く修理させていただいております。
なので、ひねりてでは
見た目にスチールよりは頼りなく見えがちだけど
実はより長期間の安定した耐久性が見込める
ナイロンタイプの芯を積極的に使用してます

それから
持ち手に入っていたのは2㎜厚くらいの樹脂製の芯と
薄めの厚紙のような素材の芯でしたが
これまた使用時によく動く部分でポッキリ割れていました(上写真 )
)
 )
)触った感じは柔らかいプラスチックのような素材です。
持ち手に厚みを持たせて軽く丈夫に仕上げるのには向いているし
作業性も良いとは思うのですが

やはりこちらもある程度の年数が経つと
劣化でこのように割れてきてしまいがちです

そこで今回ひねりてでは
この樹脂と紙芯の代わりに
床革という、厚い革を漉いたときに出る銀面側でないほうの革を使用し
さらに根ももと同じくナイロン芯(下写真 )をしっかり入れ込んで仕上げました
)をしっかり入れ込んで仕上げました
 )をしっかり入れ込んで仕上げました
)をしっかり入れ込んで仕上げました
このようにひねりてでは
もとの部品の見えない部分に使用されている材質を
同じものに揃えることにはこだわらず
元の丈夫さ以上に仕上げられると思える方法や材料があれば
それを使用しております

この芯材に関する考え方と対処法は
今までの経験の中で培われてきたもので

今現在思いつく方法の中で最良だと判断しているわけですが
他にもひねりての知らない良い方法や違う考え方もあると思います

なので、今後も修理業を続けていく中で
さらに最良の方法に出会えるよう
これからも
探究心を持って日々を過ごしていきたいなぁ
と思っております

さてさて、ちょっとご説明が長くなりすぎちゃいましたね

結構大事にしている部分なのでつい熱く語ってしまいました

ではこのつづきはまた次回ということで
つぎは底コーナー部の補強アレンジについて
またまた熱~く
 ご紹介させていただきますね
ご紹介させていただきますね

 ご紹介させていただきますね
ご紹介させていただきますね
お楽しみに

2014年05月03日
BREE書類鞄、擦り切れ補強修理と持ち手等交換 その1
すっかりお馴染様となりましたBREEさんの鞄、
紳士用のブリーフケースです

修理前の写真が
底コーナー部への落書き入りしかありませんが
気にしないでくださいね

10年近くご使用の鞄で、
持ち手全体と根ももが片方劣化しているし
底のコーナー周辺の革がすり減って色落ちしているうえ、
穴が開きかけているところもあります

例のごとく修理前の写真撮影が不十分で
底周辺の拡大写真がありません

まいど申し訳ありません

オーナー様のご要望は
持ち手と根もも2か所の交換
ファスナー引手が無くなっている2か所への引手取り付け
あとは底の擦り切れ部分の補強と
色落ち部分への着色処理です

今回のこちらの鞄

おそらく写真ではわかりにくいかと思いますが
内張りもあわせてすべて内縫いの仕上げになっており、
元と同じ見た目や仕上りに近づけるには
裏返して作業する必要があるのですが・・・
厚くて張りのある革で出来ているうえに

内張りにはクッション素材がしっかり内蔵されているため、
劣化の進んでいる現状で裏返すのはかなり危険な状態でした

ていうかいったいこの鞄どういう手順で組み立てていったの?

と思ってしまうような構造で
情けないですが、正直どうやって組み立てていったのか
はっきりとイメージすることは出来ませんでしたぁ



ひねりてもまだまだですね

そんな中でも
ひねりてなりに出来ることをあれこれ思案した末に
オーナー様へ各場所ごとへの修理案をお伝えして
ひとつひとつ選択していってもらいました

そして結果的に、
ひねりてが予想していた金額を上回る

高額、大物修理をご依頼していただくこととなりました

で、仕上りですが・・・
どんな感じになったか
一つだけ完成写真をご紹介しておきますね

あとはご自由にいろいろ想像してみてください

答えは次回のお楽しみです